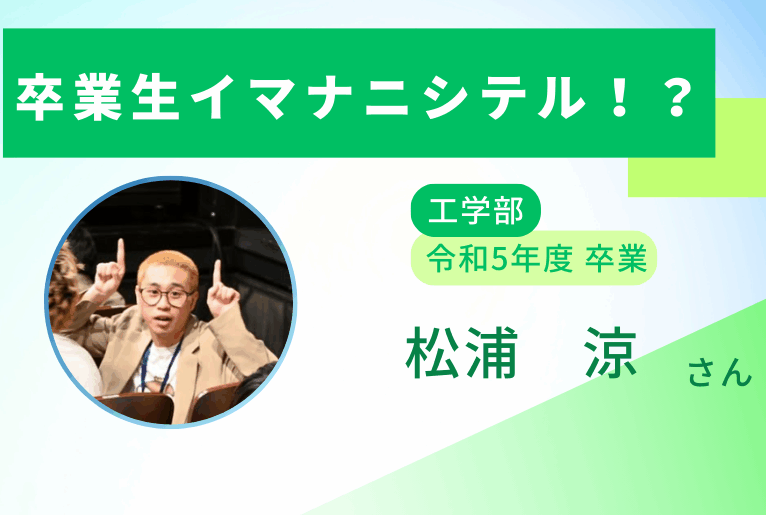Research[研究]
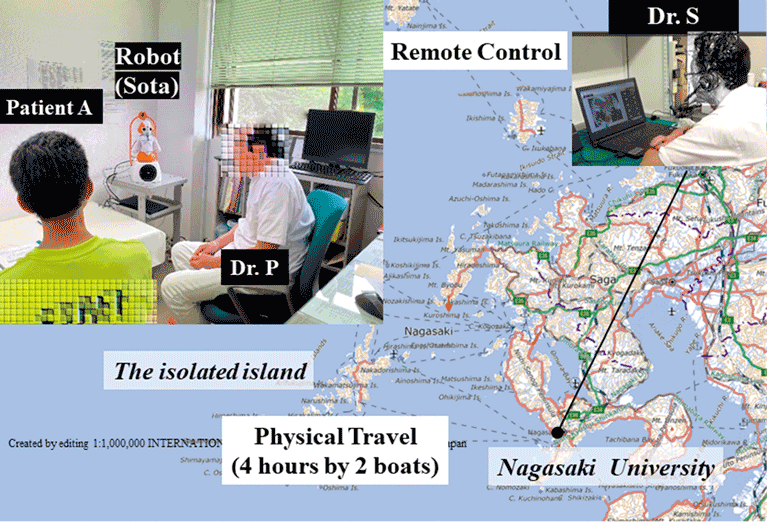
Kawahara H, Kanchi N, Kawata M, Yoshikawa Y, Baba J, Muramatsu T, Ishiguro H, Kumazaki H. Training potential of a teleoperated humanoid robot for use by a young psychiatrist during childcare leave. PCN Rep. 2024 Sep 8;3(3):e70008. doi: 10.1002/pcn5.70008. PMID: 39253714; PMCID: PMC11381314.
長崎県は日本一島が多く、1479もの離島を有します。
豊かな自然や独特の文化など、多くの魅力を有する離島ですが、その一方で、医療従事者の不足、医療アクセスの制限等のさまざまな課題も抱えています。
今回は、これらの課題に対し【共生】をテーマにロボットやAIの技術を活用して取り組んでいる長崎大学病院の熊﨑博一教授にお話しを伺いました。
多様な業種でロボット・AIの導入が進められていますが、医療の分野における応用もその一つです。
現在、ビデオ通話が主流の遠隔診療にロボットを使うメリットは大きいと熊崎教授は語ります。
ロボットは実体が診察室にあるので、患者さんは、まるでそこに医師がいるように感じることができます。
また、熊﨑教授が使うロボットは身振り手振りや体の向きを変える動作が可能です。
これにより、非言語的コミュニケーションが豊かになり、ビデオ通話よりも信頼感を高めやすいという特徴もあります。

また、医師と患者さんが対面する場合、仕草や表情に、お互い何か意味を見出そうとしてしまい、それが診察に影響を及ぼすこともあるそうですが、ロボットを介することでそのような懸念が少なくなります。
このように、ロボット・AIの導入は、遠隔診療かどうかに関係なく、従来の診察にはなかったメリットも生んでいます。
将来的には、病気の説明や治療の選択肢の提示など業務の一部をAIに任せることで、医師がより対話の時間に専念できる環境を作れるのではないかと熊﨑教授は考えます。
もちろん、ロボット・AIの導入には課題もあります。
限られた人員で対応できるよう、誰もが簡単にメンテナンス、操作ができるようにすることは非常に重要です。
また、ロボット診療を受ける患者さんの心の準備も大切です。
熊﨑教授は、ロボット診療を受け入れてもらうために、予めロボットの特徴をしっかりと説明することを心がけていると言います。
今後は、満足感や安心感、そして治療効果のバランスを大切にしながら、ロボットによる診療を改良し、患者さんに合わせた「個別化」も進めていく必要があると言います。
ただし、全てをロボットに任すのではなく、ロボットと人、それぞれの良さを「使いこなすことも大事」だと熊﨑教授は考えています。
遠隔診療に使われているこの技術は、4月から行われている大阪万博でも活躍しています。
いのちの未来館では、長崎から遠隔でCGアバターを操作し、精神疾患をもつ患者さんがリアルタイムで受付業務を行っています。
普段なら誰もが緊張してしまうような場面でも、アバターを介することで参加しやすい環境が作られているのです。
このように、ロボットを介すことで誰もが、何処にいても社会からのサポートを受けることができ、また社会に参加することができる時代が近づいています。
いつでも隣にロボットがいる世界が、もうすぐ訪れるかもしれません。
-

熊﨑 博一 教授
長崎大学病院 精神科神経科 科長慶應義塾大学医学部卒業後、慶應義塾大学医学部精神新神経科学教室入局。金沢大学子どものこころの発達研究センター在任中に米国ヴァンダービルト大学で児童精神医学を研鑽。国立精神・神経医療研究センター勤務を経て、令和5年より長崎大学医学部精神神経学主任教授・病院精神科神経科診療科長に就任。現在は長崎県基幹型認知症疾患医療センター長も兼務し、児童から高齢者まで幅広い精神医療の発展に尽力している。
-

University Research Administrator
ユニバーシティ リサーチ アドミニストレーター大学において研究者の研究環境整備や、研究開発マネジメントの強化などを担う専門職です。研究戦略立案、外部資金の獲得支援、共同研究相手のマッチング、研究プロジェクトの運営管理、研究成果で生み出された知的財産の管理・活用、研究の国際化に伴う安全保障管理など、業務は多岐にわたります。研究者と事務職員に加え、大学における第三の職種と呼ばれている新しい仕事です。長崎大学では14名ほどのURAが在籍し、長崎大学の研究力の強化、研究活動の活性化を図り活躍しています。