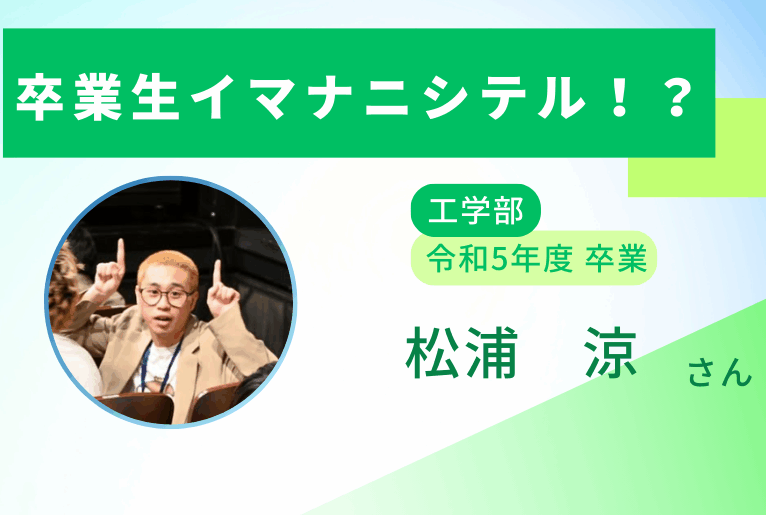Research[研究]
本稿は2025年9月18日(木)長崎新聞掲載の寄稿原稿を再編集したものです。
島が牽引する海洋再生可能エネルギー
太古の昔から、海の上では陸よりも強い風が吹き、島々の間の瀬戸には、速い潮の流れがありました。それらの強い風や速い潮の流れは、人々の暮らしにとっては、ただ厄介なだけのものであったかもしれません。しかし、現在、海洋にまつわるさまざまな技術の発展により、海の再生可能エネルギーとして、私たちが手にできる資源となる時代がきています。
五島市では、日本初の浮体式洋上風力の商用発電所建設が進んでいます。来年1月の運転開始が予定され、洋上風力と連携した漁業振興や地域活性化の取り組みも進展しています。
また、西海市の江島周辺では、着床式の大規模な洋上風力が計画中です。そこで使われる風車は、羽根1枚の長さ(115.5m)が、佐世保市にあるハウステンボスのシンボルタワーのドムトールンの高さ(105m)を超える巨大なもので、28基が洋上に設置される予定です。
一般に、本格的な洋上風力発電所は、数千億円から1兆円を超える開発投資となることもあります。これらの巨大な投資を誘発する価値の源泉は、洋上に吹いている風です。島の周辺に吹く風が、社会に再生可能エネルギーという価値を提供し、地域に新しい活動や産業をもたらします。
産学連携洋上風力人材育成コンソーシアム(IACOW)
長崎大学では、2016年4月に海洋再生可能エネルギーや次世代型の水産振興を目指した研究組織として、海洋未来イノベーション機構を創設するとともに、2022年度には、複数の大学および発電事業者へ声をかけ、「産学連携洋上風力人材育成コンソーシアム(IACOW:アイ・エイ・シー・オウ)」を立ち上げました。
長崎大学は、その代表団体として、広域の産学連携による教育の「しくみとカリキュラム」づくりを進めています。洋上風力分野が学べる大学院の正規科目8科目の開講を予定しており、既に「風車工学」、「発電所・運用メンテナンス」、「漁業共生・ステークホルダーマネジメント」、「エネルギー政策・制度」の4科目がスタートしています。
さらに、産業界と結びつく「しくみ」として、業界研究会やセミナー、インターンシップ、国内外での研修など実践的な学びを展開し、社会人向けの講座も検討するなど、洋上風力に関する高度人材の育成拠点の構築に取り組んでいます。洋上風力先進地の英国とも連携し、昨年度は学生3名がスコットランドで研修を体験したほか、五島市や西海市では、新潟大学と合同研修を行いました。経済産業省と文部科学省も長崎大学およびIACOWの提案を採択し、国とも連携した取り組みとなっています。

長崎から始まる洋上風力の未来
洋上風力は日本ではまだ新しい分野で、ウクライナ危機後のサプライチェーンの混乱や資材高騰など、事業環境の課題もありますが、将来の主力電源である再生可能エネルギーの切り札として期待されています。その最前線のプロジェクトが、ここ長崎の島々で動き出しています。
若い世代の皆さんには、ぜひ「島」と「海の再生可能エネルギー」に関心を持っていただきたいと思います。長崎大学は、欧州や産業界、島との連携をさらに強め、研究力と教育力を強化し、長崎に来れば先進のプロジェクトを学べる・活躍できるという姿を実現するために取り組みを進めていきます。

研究者情報
長崎大学 特定教授
研究開発推進機構 機構長特別補佐 兼
産学連携洋上風力人材育成コンソーシアム(IACOW) 副代表
森田 孝明