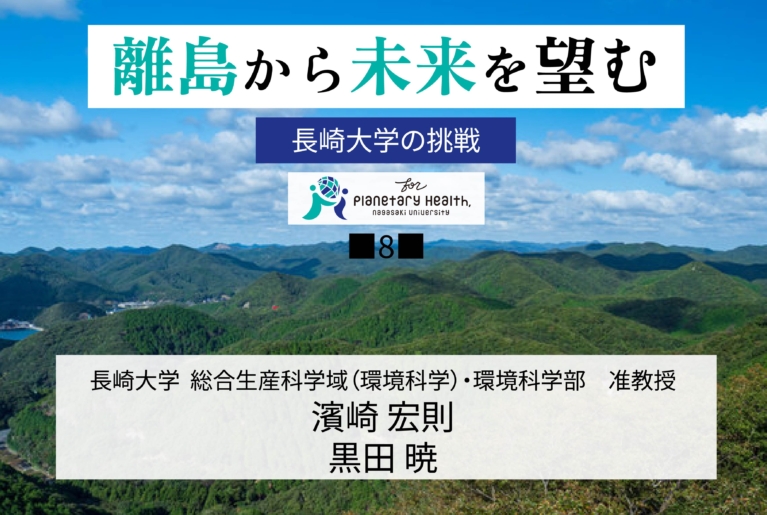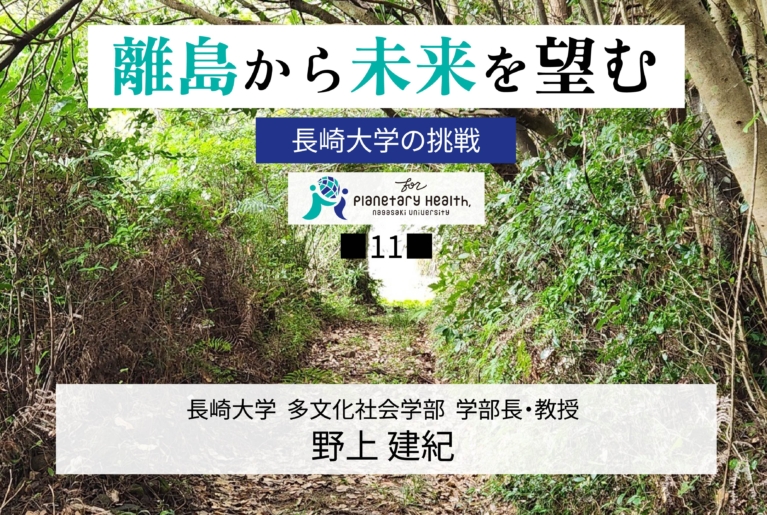Research[研究]
本稿は2025年11月20日(木)長崎新聞掲載の寄稿原稿を再編集したものです。
対馬で深刻化する獣害状況
対馬は、人よりもイノシシとシカの多い島だということをご存じでしょうか。人口約2万6500人(9月末現在)に対し、シカだけで約4万頭が生息していると推定されています。
実は対馬では、イノシシは江戸時代に一度絶滅させられ、シカは天然記念物として保護されていた歴史があります。しかし、どちらもその後急増し、田畑を荒らしたり車と接触したりと、住民生活に深刻な影響を及ぼすようになりました。山林ではシカが下草を食べ尽くして地肌がむき出しとなり、大雨時に土砂災害の危険性が増すなど、環境への悪影響も懸念されます。
住民主体で進む「捕獲隊」の取り組み
こうした状況への対策として、対馬市では捕獲隊という制度を始めました。従来、イノシシやシカなどの有害鳥獣の捕獲は狩猟免許保持者に限られていましたが、少なくとも1人の免許保持者と地域住民で捕獲隊を結成すれば、免許のない住民も箱罠の餌の交換などの補助作業ができるようになりました。これによって、各地で捕獲隊による住民主体の獣害対策が進められ、近年では人里に下りてくる有害鳥獣が減少傾向にあります。
HP用図-2-687x515.jpg)
地域調査で見えた成果と課題
私たちはこの捕獲隊に注目し、2022年から対馬市の助成を受け、有志の学生と調査を行ってきました。1年目は、捕獲隊のある地域とない地域でヒアリング調査を行い、リーダーシップがとれる人の存在などが結成を左右する要因となることが分かりました。
2年目は、捕獲隊のある全20地区を対象に生活満足度に係るアンケートを行いました。捕獲隊活動と地区の生活満足度との関連は薄いものの、活動の継続を望む声が多く寄せられました。他方で、高齢化のために多くの集落で捕獲隊の担い手が減っているという課題も浮き彫りとなりました。
そこで3年目は、どうすれば捕獲隊に関わる人を増やせるかという問いを立て、捕獲隊長を集めたワークショップを開いたり、高校生を対象にスタディーツアーを企画し若い担い手を増やせないか効果を検証したりしました。特に後者では、対馬出身でも獣害の実態を知らない若者もいることが分かり、島内外を問わず多世代に知ってもらう働きかけの重要性を認識しました。
学びの場としての対馬と今後の展望
獣害の実態を初めて知ったのは、一緒に調査を行った学生も同様です。学生にとって、獣害を受ける対馬の住民やコミュニティは、少子高齢化で担い手が減る状況下で試行錯誤する現場を生で体感できる貴重な学習の場となっています。地域コミュニティの衰退や活性化について講義でふれることもありますが、教室で学ぶだけではイメージがわきにくく、自分ごととして考えるには限界があります。対馬で調査を共にする学生は、講義で学んだ地域課題を目の当たりにして、「自分たちには何ができるだろうか」と自発的に考えるようになりました。対馬の獣害は、単に捕獲して減らせばいいということではなく、自然との共生や地域コミュニティの持続可能性といったこれからの課題を考えることのできる題材です。今後も地域の方々や学生と共に島の将来の姿を考え、行動していきます。
濱崎准教授-3.png)
研究者情報
長崎大学総合生産科学域(環境科学)環境科学部
准教授
濱崎 宏則
黒田准教授-5-386x515.jpg)
研究者情報
長崎大学総合生産科学域(環境科学)環境科学部
准教授
黒田 暁