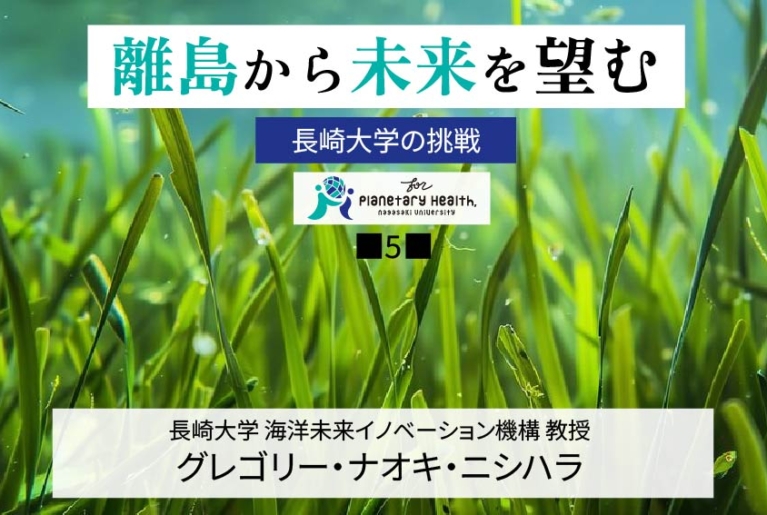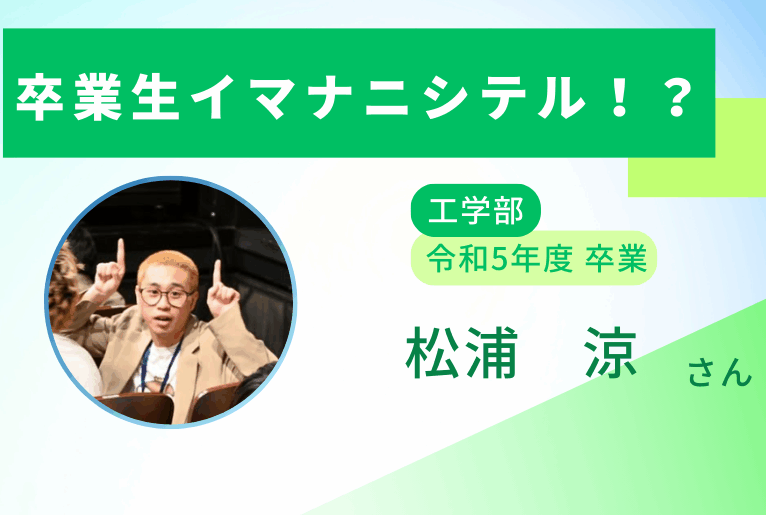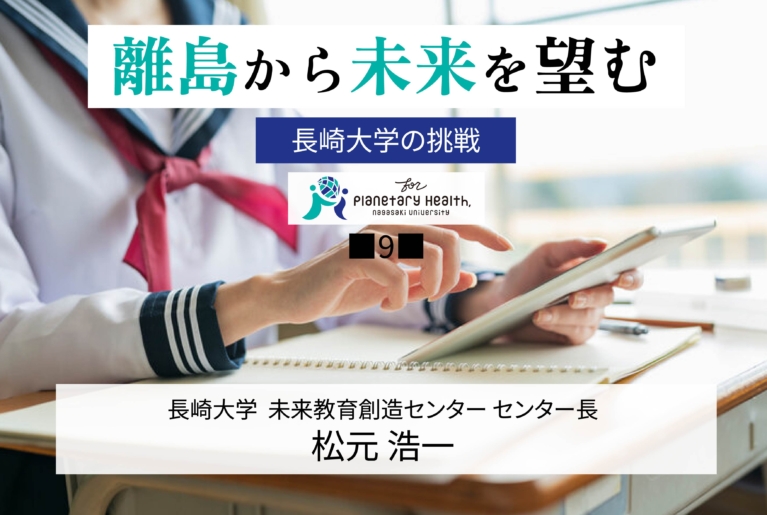Research[研究]
本稿は2025年8月21日(木)長崎新聞掲載の寄稿原稿を再編集したものです。
アマモ場の再生に向けた現地調査
私は、研究室の学生らと共に、長崎県新上五島町の有川湾に生息するアマモ場を対象に、藻場に蓄積するプラスチックごみの影響を評価しています。3年間にわたる調査で、藻場から海洋ごみを除去することで、藻場の大きさと密度(繁茂の度合い)が増加することを明らかにしました。つまり、藻場の清掃は、その再生につながると考えられます。
アマモは代表的な海草の一種であり、その群落はアマモ場という生態系を日本各地に形成します。アマモ場は漁業資源である魚などの産卵場や隠れ場となるほか、海水中の二酸化炭素を吸収する重要な役割を果たしています。ところが、増加し続ける海洋ごみによって、この「海中の草原」が失われるのではないかと懸念しています。
そのことから、プラスチックごみの蓄積がアマモ場の大きさと密度の減少につながるのではないかとの仮説を立てました。

アマモ場と海洋ごみの関係を明らかにする検証
仮説を検証するための実験は非常にシンプルな手法です。まず、定期的に藻場に蓄積したプラスチックごみなどを回収して分類し、数と重さを記録しました。次に、アマモ場の分布域や密度を、水中カメラなどを使って評価しました。さらに、アマモをプラスチックごみで覆い、枯死に至る過程を観察する実験も行いました。
そうすることで、①ごみを回収することでアマモ場の大きさと密度が増加したこと、そして②プラスチックごみはアマモの枯死につながることが明らかになりました。

海洋ごみと地球環境への影響
この研究結果の重要性を理解するためには、海洋ごみ問題の規模を把握することが不可欠です。海洋ごみとは、海に投棄された、長期間残留する固形の廃棄物を指します。その中でプラスチックごみは海洋ごみ全体の80%から95%を占めています。そのうち最大80%は陸上から海へと流れ込んでいるごみですが、海での発生源としては、放棄、紛失、または廃棄された漁具(ゴーストギア)が深刻で、これらに海洋生物が絡まってしまう「ゴーストフィッシング」として知られる現象で魚などを捕獲し続けています。

とはいえ、プラスチックそのものは社会にとって欠かせない素材であり、幅広い分野で私たちの生活に貢献しています。ですから、プラスチックによる環境汚染は、プラスチックごみの管理と、環境へ流出したごみへの対策が重要であると言えるでしょう。
海洋のプラスチック汚染と気候変動は、プラネタリーヘルスに最も有害な影響を与える二つの要因であると確信しています。海洋ごみ、特にプラスチック汚染による藻場生態系の喪失は、自然が二酸化炭素を吸収し、水産資源の成育場所として機能する能力を低下させ、それが気候変動の一因となり得ます。これらの相互に関連する問題に対処するため、さらなる科学的な取り組みと教育が不可欠となっています。

研究者情報
長崎大学 海洋未来イノベーション機構 教授
グレゴリー・ナオキ・ニシハラ