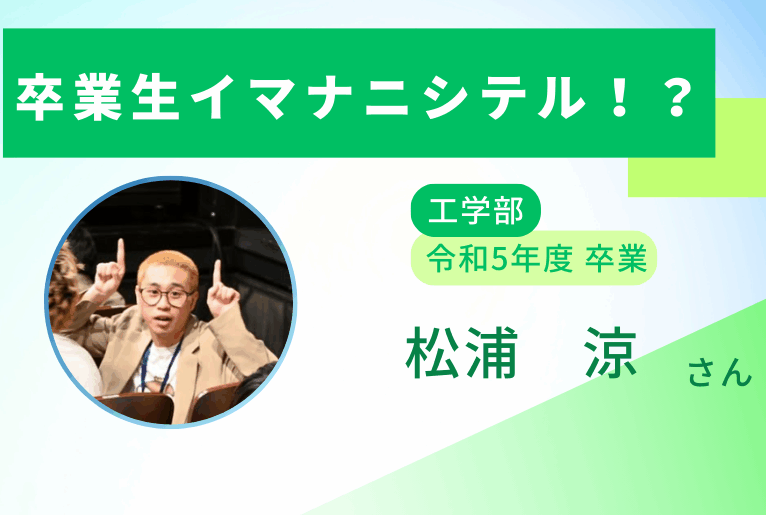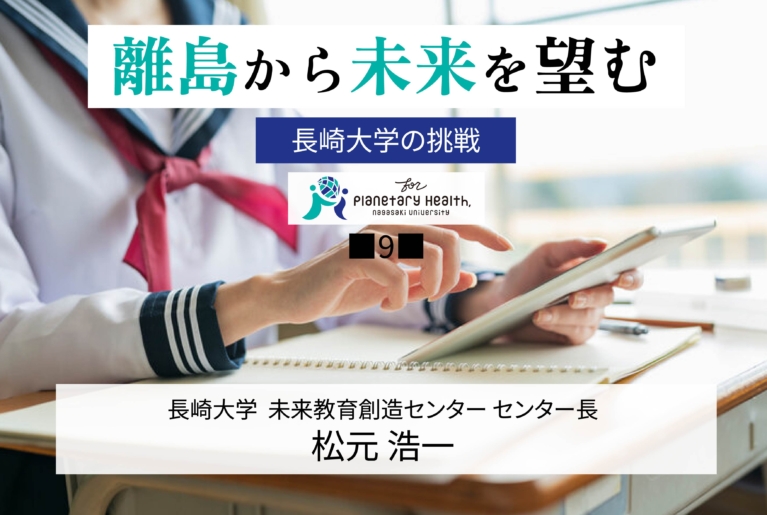Research[研究]
本稿は2025年7月17日(木)長崎新聞掲載の寄稿原稿を再編集したものです。
「シンクグローバリー・アクトローカリー」
「シンクグローバリー・アクトローカリー」(地球規模で考え、足元から行動する)。これは約20年前に私が始めた講義「環境計測学」の理念です。
私たちの身近な長崎の離島海洋環境を考える上で、まず直面するのは海流によって運ばれる海ごみの漂着問題でしょう。令和2年初め、対馬の海岸を訪れた際に大量の漂着ごみが海岸に打ち上げられているのを目の当たりにして衝撃を覚えました。しかも調べてみると、その分布は対馬の海岸全域にわたっていたのです。
ご存じのように、海ごみは環境にさまざまな悪影響を及ぼします。プラスチックごみは分解されにくく、海の中を長期間漂い、海の生き物が誤って飲み込んだり、からだに絡んだりして命を落とすこともあります。また、マイクロプラスチックが海洋生物や人間の健康に影響を与える可能性もあります。美しい海の景観が損なわれ、離島の観光業にも悪影響を与えることも考えられるでしょう。
ロボット工学の知識でごみ問題に挑む
私は、どうにか対処の糸口はないかと、専門のロボット工学の知識を生かして、まず飛行ロボットで上空から海岸ごみを撮影し、人工知能(AI)によりごみの種類分別や文字認識による発生国の特定を開始しました。
次に海洋ロボットを使って海中や海底、無人海岸地帯の海ごみの撮影を行ったところ、海底にも海ごみが堆積していることがわかりました。さらに海底の海ごみが、次の年に同一地点から再漂流していることに気づき、気象庁気象研究所や東京大学の協力を得て、数値シミュレーションにより海ごみの漂流や滞留の予測を行いました。その結果、モニタリング、漂流予測、回収、リサイクルの一連の地球規模の海ごみリサイクルプランを提言するに至ったのです。
現在は、自動採水によって海のマイクロプラスチックを自動収集する船ロボットを開発し、県内外の海域の採水と分析を行い、マイクロプラスチックの海水内含有量や海底への堆積量を調べています。このデータを基に、生物保護の観点からマイクロプラスチックの回収や固定化ができないか国内外の研究者と検討中です。さらに、開発した海洋ロボットは現在、炭素吸収量の多さで注目を集めている藻場の観測や洋上風力発電施設の点検にも使える可能性があり、ロボット工学的な進歩にも貢献しています。

左:海洋ロボット(船と水中ロボットの連携システム) 右:ロボット撮影による海底海ごみ
身近な課題から、プラネタリーヘルスの実現へ
このように、私たちは海ごみという離島の身近で深刻な問題に対し、ロボット計測や分析を通して対策検討を進めています。その成果はロボット工学の発展に繋がるだけでなく、地球規模の課題解決に繋がり、プラネタリーヘルス(地球の健康)の実現へと貢献できればと願っています。

研究者情報
長崎大学 副学長(産学連携)
海洋未来イノベーション機構教授、海洋エネルギー利用研究部門長・実海域技術開発研究推進センター長(兼)大学院総合生産科学研究科教授、医歯薬学総合研究科教授
産学連携洋上風力人材育成コンソーシアム(IACOW)代表
山本 郁夫(やまもと いくお)


-767x515.jpg)